「NICHIAではたらく」を知るマガジン

2025.05.01
【プロジェクトストーリー】青色LED開発の軌跡。ゼロから世界を照らすまでの挑戦
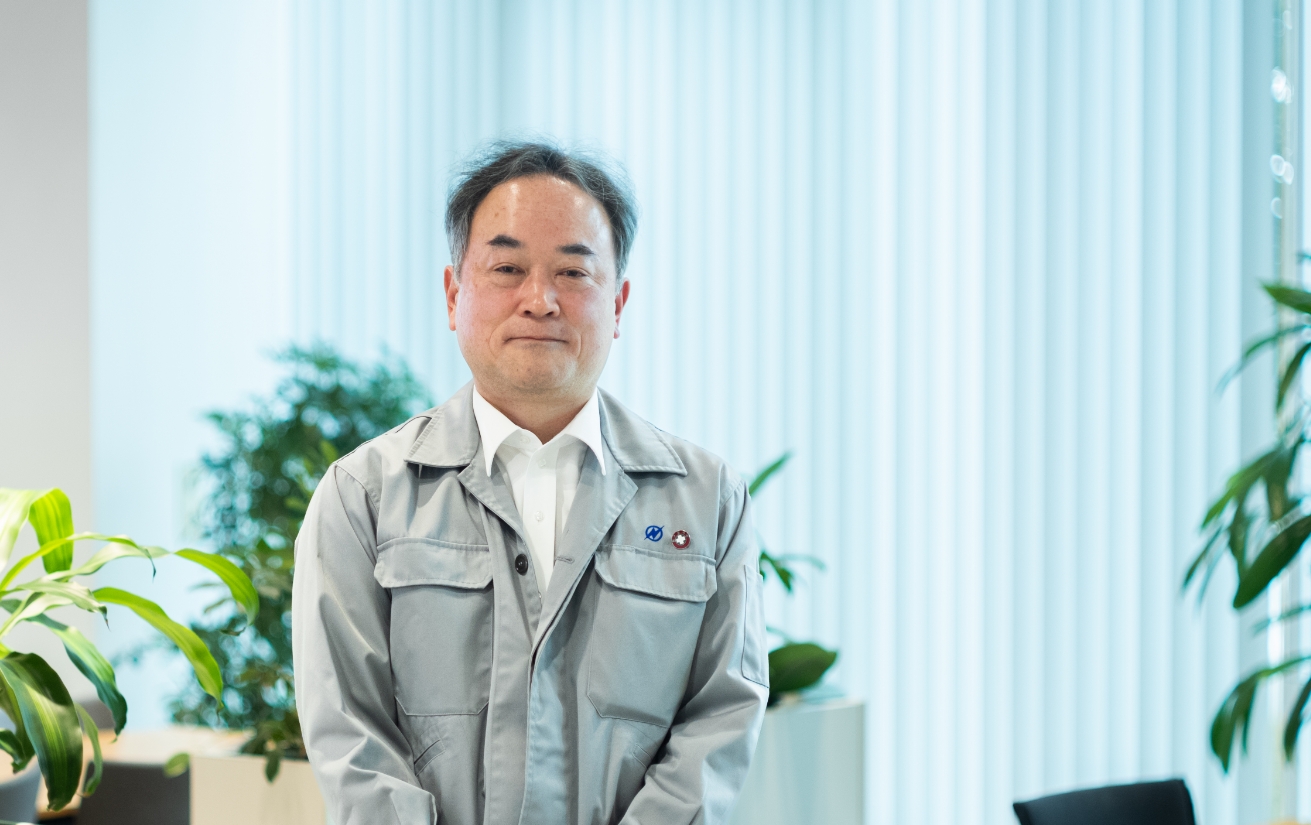
第二部門
第一生産本部 第二製造部
部長妹尾 雅之
1989年入社
※所属は2025年2月28日時点
1989年、4人のチームから始まった青色LEDへの道
青色LEDが開発された背景について、妹尾さんは、入社してからすぐ青色LEDの開発チームに配属されたとお聞きしましたが、当時の心境はいかがでしたか?
私は1989年に入社したのですが、青色LEDのプロジェクトは、ちょうどその年に始まったんです。その前に上司となる中村修二氏がフロリダ大学への留学を終えて帰国。中途採用の社員1名、私ともう一人の新入社員2名を加えた4名のチームで、NICHIAの青色LED開発はスタートしました。
当時のNICHIAは蛍光体のトップメーカーでしたが、新しい事業を模索していたところでした。その一つが光半導体だったんですね。私が大学で研究していたのは、いわゆる半導体の表面や界面における物理的な性質や現象の研究だったので、最初はEL(エレクトロ・ルミネッセンス)関連の部署へ配属されるのかなと思っていました。ところが、入社してすぐに専門外である「青色LEDの開発を」と言われ、とても驚いた記憶があります。
青色LEDの現状も知らなかったんですよ。世界ではどのように研究されているのか、どういう形で進められているのか――。それすらも知らなかったので、何から手をつけるべきかもわかりませんでした。

当時、青色LEDを取り巻く状況は、どのようなものだったのでしょうか?
LEDの歴史自体は1906年に始まり、赤・黄緑・黄・橙などのLEDがすでに開発されていました。しかし、白い光を生み出すには、光の三原色である赤・青・緑が揃わなくてはいけません。世界中の大学や研究機関、メーカーが必死に青色LEDの研究を進めていた状況でした。青色発光に必要な材料が探し出され、さまざまな研究の結果、実現の可能性が高いと見られていたのが、SiC(シリコンカーバイド)、ZnSe(セレン化亜鉛)、GaN(窒化ガリウム)です。
青色LEDの作成自体は、1970年代にアメリカのRCA研究所が成功しています。ただ、これは外部量子効率が低く、非常に暗かったため、実用化には至っていません。その後、ごく少量だけ販売されたものもありましたが、どれも輝度が足りず、寿命も非常に短かったことから「20世紀中に青色LEDの量産化は不可能である」といわれていました。それほど難しい研究・開発だったんですね。

実現を阻む3つの高いハードルを越えて
青色LEDの開発にあたり、特に障壁となったのはどのような点でしたか?
当時世界の青色LED研究の主流は、II-VI族の材料、特にZnSe系にフォーカスした研究でした。こちらはデータも豊富にありましたし、実現の可能性が高いと目されていたんですね。どこも盛んに研究をしていたと記憶しています。
しかし、私たちが選んだGaNは、良質な結晶が出来ずほぼ光らないため、皆があきらめた材料だったんです。つまり、世界とはまったく別のベクトルからスタートした研究でした。中村氏が結晶の成長を担当、私を含めた3名が結晶評価と素子化を進めるための実験装置の導入を中心に進める担当になり、ラボを立ち上げていきました。
主な障壁は3つです。最初のハードルは、GaNの結晶を成長させることでした。しかし、いくら反応させても良質な結晶ができません。表面が荒れ果てた摺りガラスのようなものばかり。ひたすらMOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)という結晶成長装置の改良をしながら、何をやっても結晶にならない真っ黒な失敗作の膜を評価する日々が続きました。
いかにして良質のGaN単結晶が得られるか――。ここをクリアできなければ、次の段階に進むことすらできません。1年があっという間に過ぎ、2年目になってからわかった独自のバッファ層の導入と実験装置の改良で、やっと良質なGaN単結晶の成長に成功しました。
次のハードルはP型結晶の実現です。半導体はその構造と特性によってN型とP型に分けられます。LEDを作るためには、N型結晶とP型結晶が必要不可欠になりますが、GaNに関してはP型結晶がどうしても実現できません。
その原因究明と、作成方法を探るために次の1年を費やしました。P型結晶の作成について、書かれた論文を参考に追試してもまったく出来なかったんです。安定したP型結晶の作成は、いろいろ試してみて、やっと実現できました。

一つの大きなハードルを越えるには、1年の歳月が必要だったんですね。
やはり時間は必要でした。最後の大きなハードルは、駆動電圧を下げつつ出力を上げること。P型結晶の作成によってPN接合が可能になっても、そのままでは暗い上に駆動電圧が高すぎるため、残念ながら実用には程遠い状態でした。
駆動電圧低下に関しては、私が主に担当したウェーハプロセスの部分です。これがまた厄介で、駆動電圧が下げられる電極構造ができたとしても、P型結晶自体の抵抗が高く、電極が広がらない。ごく一部しか光らないので、適切に光が取り出せないという問題がありました。
そこでメンバー全員で考えたアイディアが、電極を透明にして、効率的に光を取り出すという解決方法です。いわゆる「P型透光性電極」の開発ですね。この頃にはInGaN(窒化インジウムガリウム)やAlGaN(窒化アルミニウムガリウム)といった高効率化に必要不可欠な混晶の開発も進み、品質の高いInGaN単結晶の成長にも成功しています。スタートから4年目に当たる1992年のことでした。その後、InGaNの発光層をAlGaNクラッド層で挟み込むダブルヘテロ構造などを実現し、世界初の実用水準の明るさを備えた青色LEDの誕生へとつながっていきます。

メンバー全員の一つひとつの積み重ねが、3つの大きなハードルを越える原動力になったことがよくわかりました。特に思い出に残っているのは、どの瞬間ですか?
一番印象に残っているのはP型結晶ができた瞬間です。その日は「ひょっとしたら……」という予感めいたものがありました。当時の論文は電子顕微鏡で用いるような細く絞った電子線を、時間をかけてウエハーから切り出した小片に照射するんですが、思いきって、たまたまラボにあった電子ビーム蒸着装置を試してみたんです。
通常では絶対に考えられない方法なんですよ(笑)。非常に高いエネルギーで電子線を当ててみたら、あれほどできなかったP型結晶が完成している……。何度も試行錯誤を重ねましたが、セオリー通りでは決して到達できなかったでしょう。あの日の夕方に味わった喜びは今でも忘れられません。
柔軟な発想と挑戦の精神、自由な環境が不可能を可能に
プロジェクトのスタートからわずか5年で青色LEDの開発と量産化に成功したわけですが、当時のNICHIAの研究および開発環境はいかがでしたか?
当時のNICHIAは、社員数でいえば400名足らずの小さな会社でした。私が378番目の新入社員だったんですよ。研究や開発の環境は、非常に自由かつアグレッシブでしたね。失敗してもレポートや報告書を書くより、別の角度から挑戦していく姿勢が当たり前。一度、実験で結果を出すことができたら、再現性や優位性の確認は後回しで、すぐに次の段階を検討していました。形式的な会議や机上で考えるのではなく、ざっくばらんに議論しながら手を動かす環境だったんです。
経営陣も細かい指示を出すのではなく、研究や開発に従事する社員を信頼し、自由にチャレンジさせてくれました。今もその風土は受け継がれていると感じます。社員に情熱とチャレンジ精神があり、組織にとって必要な事柄であれば、決して否とは言いません。むしろ、後押ししてくれるでしょう。
設備投資にしてもそうです。出社時に社長とお会いしたときに「こういう設備が必要なので、お願いいたします!」と申請書を出したら、その場で内容を確認して即決していただきました(笑)。さすがに組織としての規模が大きくなった今では無理だと思いますが、当時のスピード感は段違いでしたね。
また、部門間の垣根が低く、他部署の専門家に気軽に相談できる企業文化も、その頃から変わらない気がします。たとえば、必要な機器を自作する場合、先輩や他部署の技術者が親身になって教えてくれました。こうした風土や文化があるからこそ、実験や試作も迅速に進められましたし「青色LEDを自分たちの手で実現しなければ!」という気概にもつながっていったんだと思います。わずか5年で研究開発から量産化まで達成できる土壌がNICHIAの強みです。
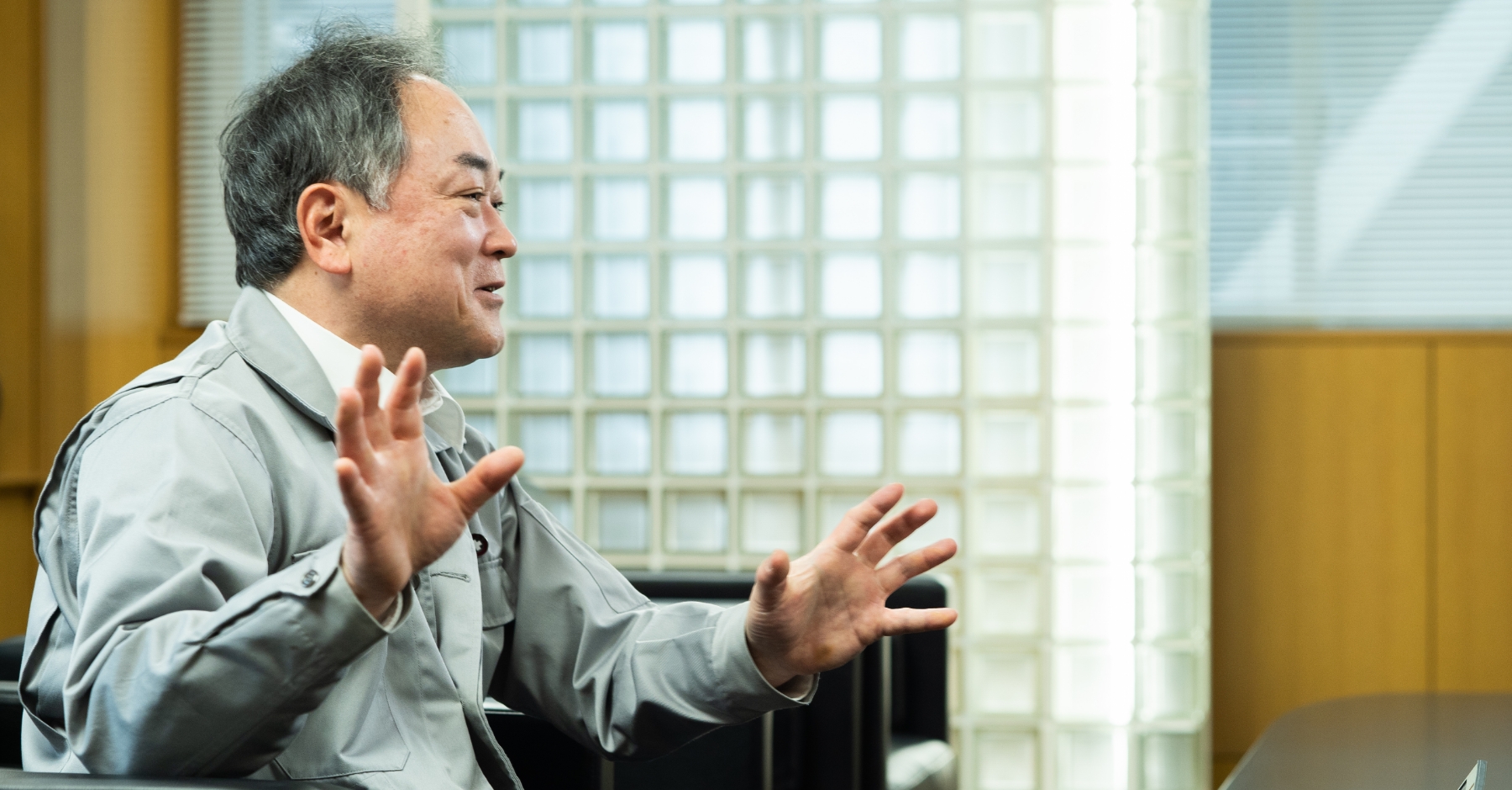
妹尾さんたちが作った青色LEDから白色LEDが生まれ、世界が大きく変わりました。
そうですね。青色LEDの実用化によって光の三原色である赤・青・緑が揃い、照明やディスプレイの分野に革命が起こりました。いつの間にかフィラメント電球がなくなり、蛍光灯が消え、街路の水銀灯や信号などがLEDに置き換わっています。テレビも分厚いブラウン管から薄型液晶ディスプレイに変わり、自動車のヘッドライトも明るく、デザインの自由度が向上しました。目に見えないほど小さな発光素子が、私たちの世界を大きく変えつつあります。
最後にNICHIAの技術者を目指す方々へメッセージをお願いいたします。
まだ誰も見たことのない製品の研究や開発では、頭で考えるよりも、実際に手を動かして試してみる。それが何よりも大切です。机の前で悩んでいても仕方ありません。まず悩む前にやってみる。そして、出てきた結果に対して考察する――。もちろん、結果は重要ですが、そこに至るまでの経緯と努力にこそ、たくさんのヒントや新しい事実が隠されているんです。固定観念にとらわれず、挑戦を続けることで、思いがけないブレイクスルーが生まれる場合もあります。自分の課題に興味を持ち、楽しみながらチャレンジしてください。



