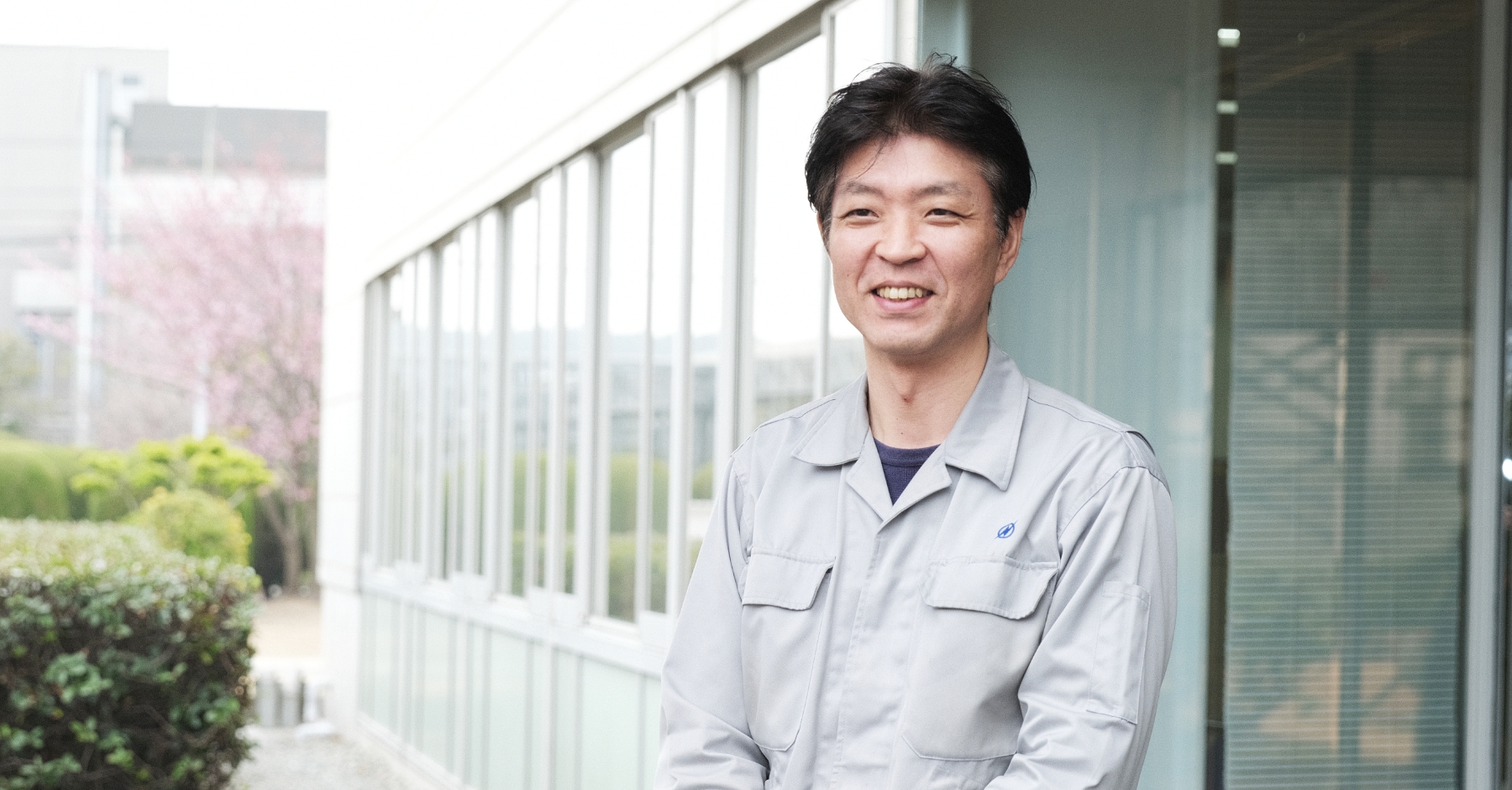「NICHIAではたらく」を知るマガジン

2025.04.25
【プロジェクトストーリー】蓄電池の技術革新が描く、未来社会に向かって

第一部門
技術本部 技術部
部長津田 拓也
1998年入社
※所属は2025年2月28日時点
三元系材料がもたらす可能性を追求
今回はリチウムイオン電池材料の開発プロジェクトについてお話を伺います。まずリチウムイオン電池とは、どのような特性を持った電池なのでしょうか。
乾電池は「一次電池」と呼ばれ、一度放電すると使い切りになります。それに対してリチウムイオン電池は「二次電池」と呼ばれるもので、充電して繰り返し使えるのが特徴です。
内部構造としては正極材と負極材があり、その間に電解液とセパレーターがあります。セパレーターは正極と負極が物理的に接触しないようにするための樹脂製の膜です。この構造によって、リチウムイオンが正極と負極の間を行き来することで充放電が可能になります。当社では「正極材」の開発や製造を行っています。
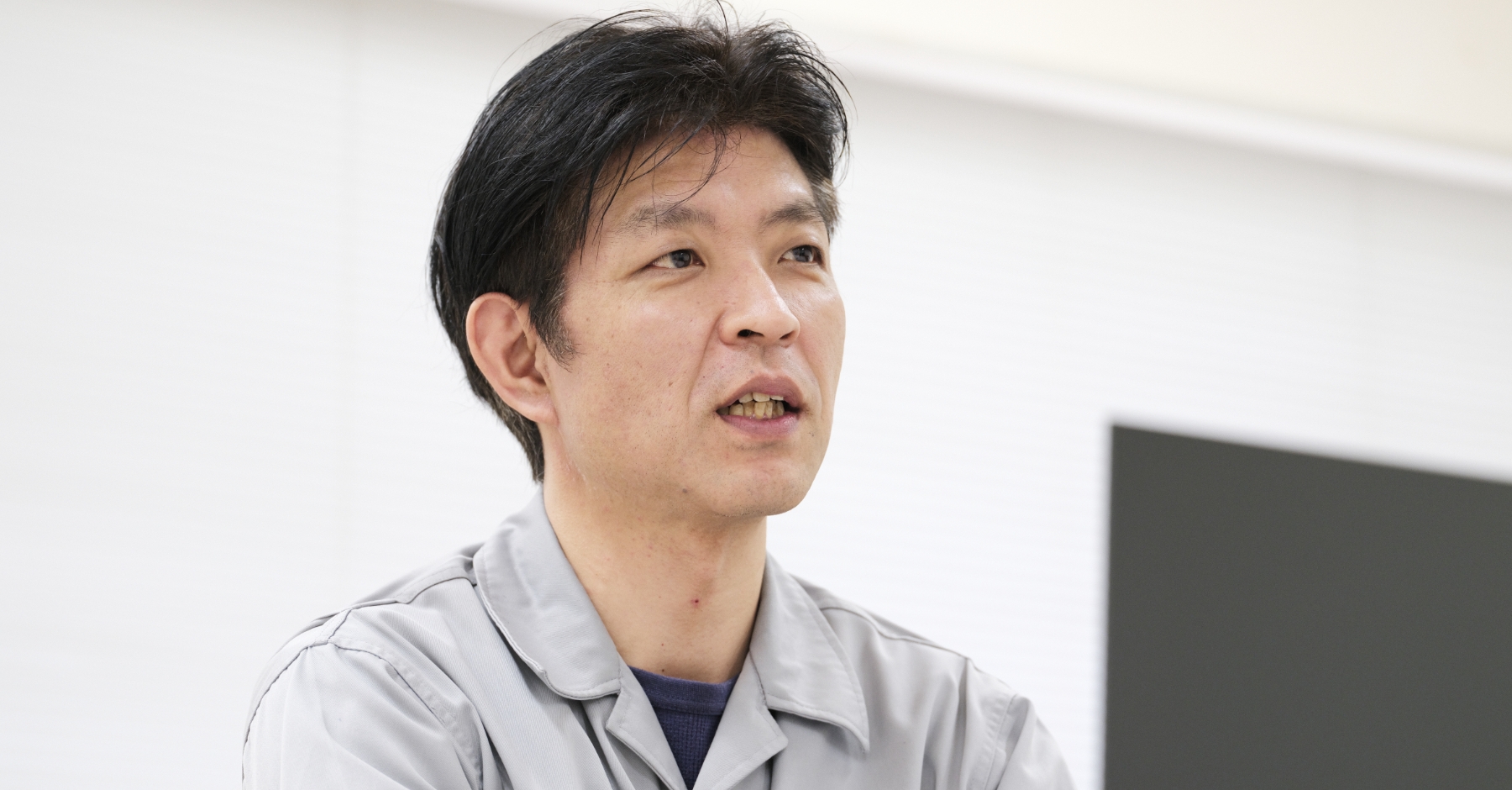
現在、リチウムイオン電池はどのような市場で活用されていますか?
繰り返し充放電が可能なため、自動車の電動化に伴って車載分野を中心に拡大しています。車載用に用いられている主な正極活物質(電極材料)の一つが、Li(NiCoMn)O2の化学式で表される「三元系材料」と呼ばれる物質です。
私が入社した1998年には、すでにLC(リチウムコバルト酸)正極材料が量産化されており、携帯電話やPHS、ノートパソコンなどの携帯情報機器に使用されていました。一方、コバルトの一部を比較的安価なニッケルとマンガンに置換した「三元系材料」は性能面でLCに劣る部分があり、当時はまだ実用化されていませんでした。
では「三元系材料」のメリットは、どういった点にあるのでしょうか?
三元系材料の大きな特徴は「バランスが取れている」という点です。エネルギー密度、出力、耐久性、安全性、コスト、すべての性能において極端に優れているわけではありませんが、致命的な欠点がないのです。また、ニッケル、コバルト、マンガンの比率を変えることで特性を変化させ、用途に応じた電池開発がしやすいという柔軟性も大きな強みとなっています。
ニーズの先取りで新たな歴史を切り拓く
初めて三元系材料が採用されたのは、いつ頃ですか?
2004年、NTTドコモのFOMA携帯向けに、初めて三元系材料が採用されました。当時のFOMA用電池では、正極材と負極材の劣化速度のバランスを取るために、三元系を少量ブレンドする形で導入されました。あくまで補助的な役割でしたが、市販品に三元系が初めて使われたという意味では重要な転機でしたね。
その歴史的な転換点にNICHIAの正極材が採用されたのですね。
はい。当時から「将来的には必要になる」と電池メーカーからの要望もあり、ニーズを先取りする形で継続的に研究開発を行っていました。開発にあたっては、電池メーカーからの評価結果を待つだけでなく、当社で電池を特性評価ができる体制を整えていたことも大きな強みだったと言えます。

自身が開発に関わった三元系材料が初めて採用され、世の中に出たときの気持ちはいかがでしたか?
休日返上で試作や評価を行うことも多く、正直に言って苦労の連続でした。でも、それだけに製品化されたときの喜びはひとしおでしたね。
そうした技術の積み重ねにより、近年では三元系材料が車載用としても使われるようになったと。
それまでの主流だったLCは電池性能が抜群である反面、安全性やコスト、資源リスクなどの欠点を抱えていました。それに比べ、三元系材料は致命的な欠点がないことに加え、ニッケル、コバルト、マンガンの組成比率を調整することで、各種用途に適応した電池開発が可能になります。この柔軟性を活かすことで、従来のモバイル機器用途の小型電池から車載用途の大型電池に採用されるようになりました。
今後は、どのような三元系材料が市場に求められると思いますか?
車載動力用のリチウムイオン電池と言っても、エンジン走行をモーターでアシストするハイブリット車をはじめ、蓄電池を備え外部充電可能としたプラグインハイブリッド車、蓄電池とモーターのみで走行する電気自動車など、求められる電池や正極材の性能は大きく異なります。当社では高度な演算処理や粒子設計の最適化により、お客さまが求める三元系材料の開発を進め、多くの商品化を達成することができています。
世界をリードする評価体制とスピード感
三元系材料の用途が、さらに広がっていく可能性はあるのでしょうか?
もちろんです。宇宙開発をはじめ、電動工具やデータセンターのバックアップ電源、大規模な定置用蓄電システムなど、すでにさまざまな分野で開発や実用化が進んでいます。特に太陽光発電のような不安定な電源を安定化させるための用途として、ますます蓄電池の需要が高まっていくはずです。現時点では車載用途の市場規模が大きいですが、それ以外の分野も伸びていくと考えています。
津田さんが考えるNICHIAの強さとはなんでしょうか?
国内を中心とした多くの電池メーカーと正極材の取引があり、それぞれの要求に応じて多岐にわたる材料開発をスピーディーに進められる点です。このスピード感の背景には、頻繁な打ち合わせを通じた密な連携があります。お客さまからの評価結果を受けて、すぐに改良品を出す。その開発サイクルの速さが大きな武器になっています。
また、評価技術の開発も同時に進めており、社内評価とお客様評価の相関をとることで効率的な開発を行える体制を築いています。
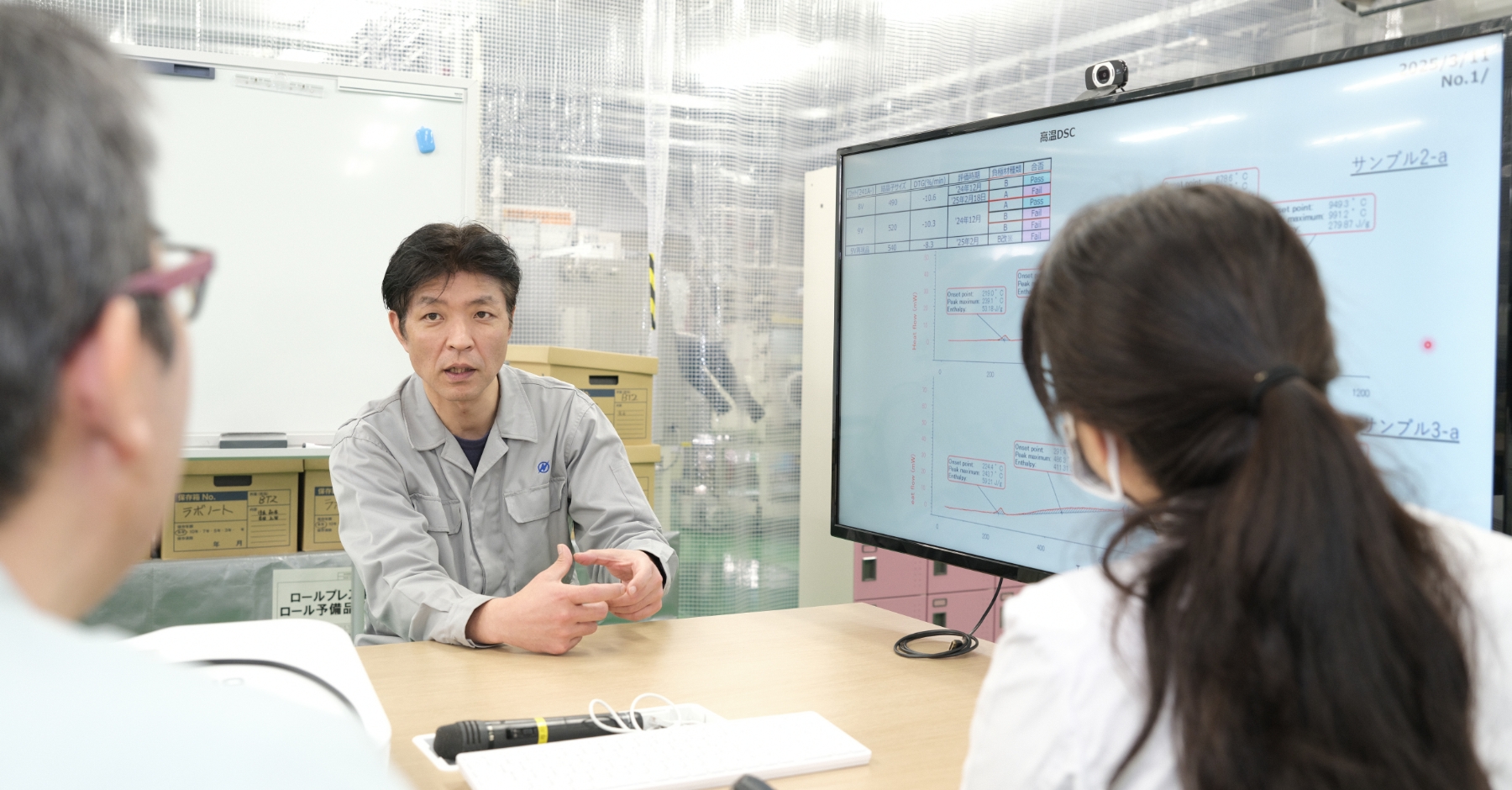
電池材料開発の社会的な意義や将来性を、どのようにお考えですか?
電動化はCO₂削減の観点からも重要なテーマです。ガソリンや軽油などの内燃機関から電池とモーターによる電動化への移行と化石燃料への依存を減らし、環境負荷を軽減することができます。ただし、電気自動車の製造工程や電力の発電方法によってもCO₂排出量は変わりますし、電池材料の製造にもエネルギーを使います。今後はリサイクル技術の進展により、原料の再利用が進めば、環境負荷は大きく減らせるはずです。
失敗の積み重ねが、成功への道標となる
仕事をする上で大切にされている信念を教えていただけますか?
一番大事にしているのは「電池の中で何が起きているのか」というロジックを持って開発に取組むことです。電池というのは本当に“ケミカル”な製品で、正極と負極、電解液、セパレーターといった複数の部材の組み合わせの中で常に副反応が起きています。ガスが発生して電池が膨らんだり、粒子が割れて劣化が進んだり、抵抗が増加したりといったことが頻繁に起こるのです。
そういった現象の原因を理解することなく闇雲に試作を繰り返しても、なかなか良い結果にはたどり着けません。評価部門とも連携して、材料の合成・評価・解析を一体で進めることが大事です。お客さまの評価結果も参考にしつつ、社内の評価でもしっかりとロジックを立て、次の試作につなげていく。そんな工程を繰り返しながら、お客さまに最適な材料を提案しています。
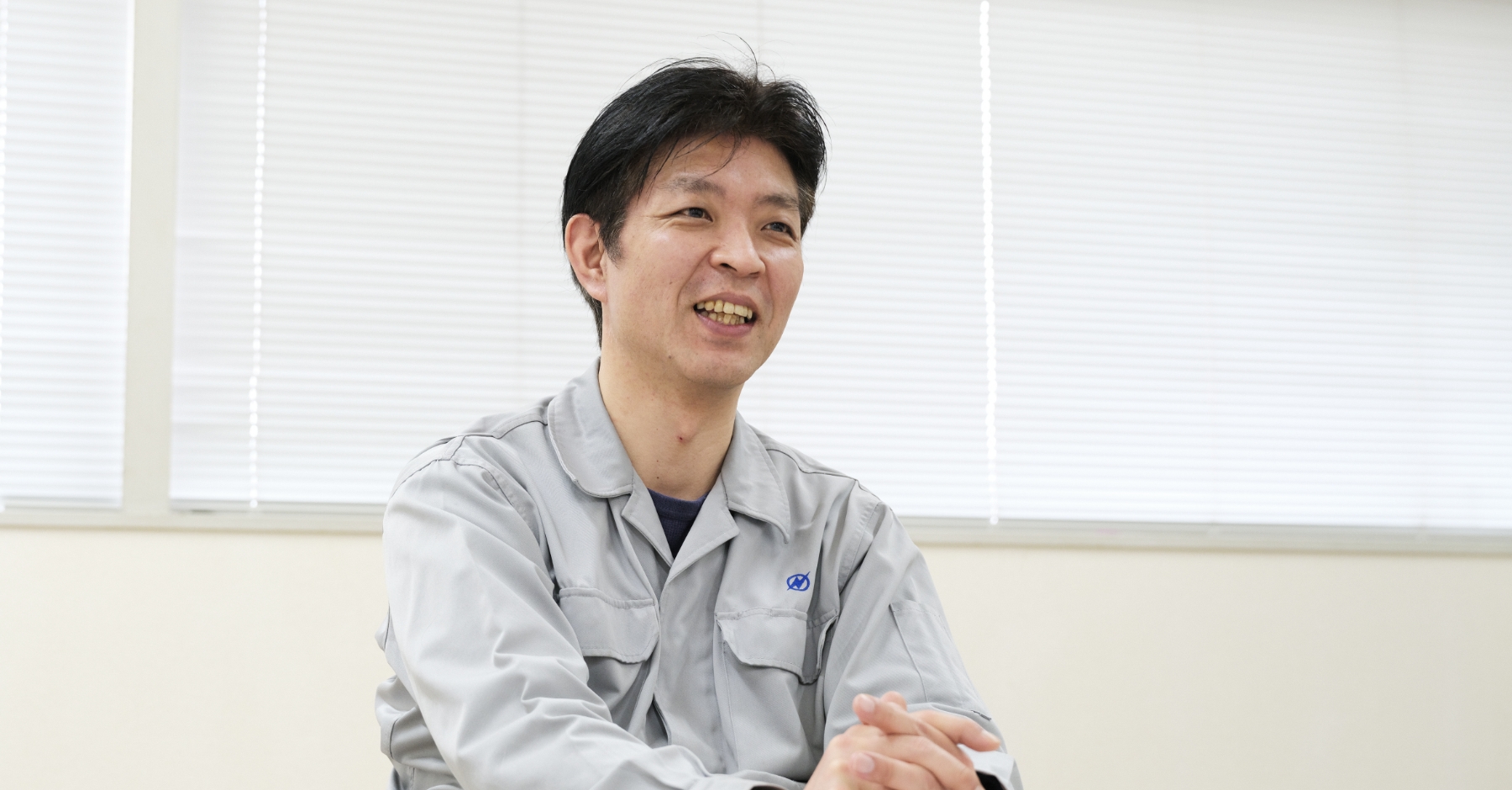
そうやって未知の技術を一つずつ獲得していくのですね。
たとえ試作がうまくいかなくても「このやり方は駄目だった」ということが分かれば、それも大きな成果です。失敗を積み重ねていくことで、正解の道に近づいていく。そういう姿勢を大事にしています。また、周りの若い人たちには「楽しんでやってほしい」とよく話しています。私のように「ものつくりをやりたい」とこの世界に入ってきたわけですから、その気持ちを忘れずに、しんどい時期を乗り越えていってほしいなと思っています。
今後はどのような挑戦をしていきたいとお考えでしょうか?
理想を言えば、すべての電池メーカーに対して「これを使えば間違いない」と言われるようなオールマイティーな材料を開発できればいいのですが、現実はそう簡単ではありません。サンプルワークや技術的な打ち合わせを通じて、今まで以上にお客様にとって最適な材料を短期間で提供できるよう、評価技術の高度化や体制強化を進めていきたいと考えています。当社の強みである製造業としての基盤を持ちつつ、お客様に寄り添い、共に最適解を探す。それがNICHIAのやり方ですから。